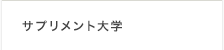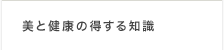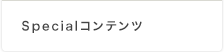- サプリメントの「サプリ」TOP
- 気になる症状
- 口臭
- 口臭に良いサプリメント成分
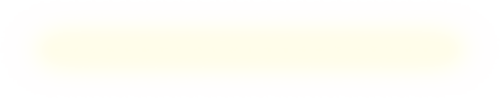
【口臭に良いサプリメント成分】

■口臭にサプリメントが良い理由
人と話しているときに気になる口臭。会話中の相手の口から臭いがしたことがあるという方も多いでしょう。自分では気づきにくいので、気づかないうちに口臭を発していることもあるかもしれません。
そんな口臭には、いくつか原因があります。1つ目は歯周病をはじめとした病的口臭。2つ目は舌についた汚れ、または唾液に存在するタンパク質が、口内の菌によって分解されることによる生理的口臭。3つ目はニンニクやニラなど臭いの強い食べ物を食べたときに発生する一次的な植物由来口臭です。
口臭が気になる方は、サッと手軽に取れるサプリメントを活用してみましょう。ここでは、口臭対策に良いとされている成分とその理由についてまとめています。
■口臭に効くサプリメント成分まとめ
クエン酸
唾液の分泌を促し臭いを防ぐ
「酸っぱい」と感じる食べ物に含まれていることが多いクエン酸。このクエン酸特有の酸味成分は、体内に入った糖を分解してエネルギーに変える力を持っているのです。また、ミネラルを吸収しやすい体にして、 体に疲れが溜まるのを防いでくれます。無色または白色をしていて、熱に強く水に溶けやすいのが特長です。
クエン酸は唾液を出やすくする作用もあるので、口が渇くのを防ぎ、細菌の増加を抑制します。口臭対策に最適だと言われているのはこの点もあるのです。
口臭を防ぐ食べ物として有名な梅干しにもクエン酸が含まれています。
食べ方としては、梅干しにお湯を注いだあと食べる方法があります。梅干しが苦手だという方は梅酢を飲むと良いでしょう。自分流にアレンジしたホットドリンクを作ってみるのも良いかもしれません。朝起きたときの摂取がベストなタイミングです。
梅干し以外にも、オレンジやレモンなどの柑橘系の果物に多く含まれているので、食後のデザートとして取ってみるのもおすすめです。
口臭の原因はさまざまですが、口内が渇き雑菌が増加するのが大きな原因の1つ。口の潤いを保ちやすくするには、クエン酸が含まれる食べ物を摂取するのが最適です。もし、毎日の食事で摂取が難しい場合はサプリメントも活用してみましょう。
カテキン
抗菌作用で口臭をブロックする
数種類あるポリフェノールの中のフラボノイドに属されるカテキン。お茶に多く含まれていることで、名前を聞いたことがある方も多いでしょう。カテキンは植物に含まれている成分で、辛さや苦み、色素などの役割をしています。緑茶を飲むと感じる苦味は、このカテキンによるものです。
緑茶以外にウーロン茶や紅茶にも含まれていますが、1番多いのは急須で煎じる緑茶。ペットボトルの緑茶にもカテキンは含まれているものの、1度に効率的に摂りたい場合は、少し手間はかかりますが、煎じたお茶がおすすめです。そのほかにも、さくらんぼやぶどうといった果物や、小豆や大豆といった豆類などにも含まれています。
カテキンには抗菌作用があり、口の中にいる大量の細菌にアプローチして口内の健康に影響をもたらします。細菌は口臭の原因にもなるので、積極的にカテキンを摂取することで嫌な口臭も防ぐことができるのです。
口臭は虫歯が原因になっている場合もあります。虫歯は、人の口の中にいるミュータンス菌という細菌によって酸が発生し、歯の表面のカルシウムが溶かされることで起こります。カテキンは、そんなミュータンス菌の増殖を抑制する力を持っているので、虫歯を予防しながら口臭の防止が望めます。
柿タンニン
強い臭いもパワフルに抑える
柿に含まれる柿タンニンも口臭予防が期待できます。
昔から日本の人々に親しまれている果物、柿。糖度が高く、甘く優しい味がするのが特長です。そんな柿ですが、りんごやなしなどの果物に比べて人気が低く、日常的に摂取する人は少ないそう。
しかし、柿には含まれる柿タンニンという成分には口臭防止効果があり、気になる臭いを抑制してくれるといわれています。その実力は、臭いを抑えることで有名な緑茶の約7倍。強力な消臭効果を持つ成分です。
食後にりんご・なしを食べたときの口臭と、柿を食べたときの口臭を確かめる実験で、りんごとなしを食べたあとは口臭がひどく、柿を食べたあとは臭いがしないという結果になったといいます。また、ニンニクやニラといった臭いの強い食べ物が原因の口臭にも良いとされているので、食後にデザートとして食べると良いでしょう。
それほど高い効果が期待できる柿タンニンは、口臭を抑えるだけでなく生ゴミのような強烈な臭いも抑える効果が期待できるのだそうです。
口臭が気になる、または予防したいという方は、意識して柿タンニンを摂取することが望ましいでしょう。毎日柿を摂取するのが難しいという方や、柿はあまり好まないという方などもいるかもしれません。そんなときは、柿タンニンが含まれるサプリメントでの摂取がおすすめです。
なた豆の成分
臭いの大きな原因となる歯周病を予防する
マメ科の1年草であるなた豆。比較的大きな植物で、丈は5メートル、さやは40センチ以上にも成長します。マメも大粒で3センチほどあるのが特長です。
なた豆は、調理して食べるほか、煎じてお茶にして飲んだり、歯磨き剤に活用したりと幅広く使われています。
なた豆は口腔内の細菌のバランスを整える効果が期待でき、最近では歯周病の予防策として摂取している方も多いそうです。繰り返す歯周病で悩んでいる方には、毎日なた豆茶を飲み続けることで早期改善が望めると言われています。
なた豆は別名「膿取りマメ」と呼ばれており、蓄膿症や歯周病の膿を取り出す働きも期待できます。歯周病は進行すると膿が溜まる歯槽膿漏になり、口臭の原因になるもの。生活の中になた豆を取り入れることで、歯周病が原因として生まれる膿を排出させ、臭いの原因を取り除いてくれるのです。
そのほか、なた豆には腸内環境を整える成分も含まれているといわれていおり、悪玉菌が原因の口臭を抑える働きもあります。
最近では、簡単に口臭ケアできるサプリメントもあります。お茶や歯磨き粉と併用して歯周病をはじめとした口臭の原因にアプローチするのがおすすめです。
<参考文献>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【口臭をもっと知る】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【口臭をもっと知る】
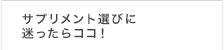
-

-
あ行
- 亜鉛 青汁 アガリクス アサイー 麻の実 明日葉 アスタキサンチン アフリカマンゴノキ アミノ酸 アラキドン酸 アルギニン アルファリポ酸 アロエ アワビ EPA イソフラボン イチョウ葉 イミダゾールジペプチド イワシペプチド ウコン エキナセア エクオール エゾウコギ L-カルニチン オメガ3 オリーブ葉 オリゴ糖 オルニチン
か行
- 海藻 カカオフラバノール 柿渋エキス 核酸 カシス ガセリ菌 カテキン カボチャ カリウム カルシウム ガルシニア 甘草(カンゾウ)エキス キトサン ギムネマ キャッツクロー GABA 金針菜 クエン酸 クマザサ クラチャイダム グラブリジン グリシン クリルオイル グルコサミン グルコシルセラミド グルコポリサッカライド グルタミン クレアチン 黒酢 クロセチン 桑の葉 酵素 酵母 高麗人参 コエンザイムQ10 ココナッツ コミフォラムクル コラーゲン コンドロイチン
さ行
- サイリウム ザクロ サジー SAMe含有酵母 サラシア サンゴヤマブシタケ シークヮーサー ジオスゲニン シトルリン シャンピニオンエキス ショウガ シルク シルク(グリーンシルク、シルク粉末) 白インゲン豆 水溶性食物繊維 スクワレン(肝油) すっぽん スピルリナ 炭 スルフォラファン セサミン セラミド セリン セントジョーンズワート その他
た行
な行
は行
- ハネセンナ(キャンドルブッシュ) パルテノライド バレリアン BCAA ヒアルロン酸 ビオチン ピクノジェノール ビタミン ビタミンE ビタミンA ビタミンC ビタミンB群 ヒトデ ビフィズス菌 非変性Ⅱ型コラーゲン ヒマワリの種 ビルベリー プーアル茶 プエラリア・ミリフィカ フォルスコリ フコイダン(ガゴメ昆布) ブドウ ブドウ糖 プラズマローゲン プラセンタ ブラックジンジャー ブルーベリー プロテイン プロポリス βカロテン βクリプトキサンチン βグルカン
ま行
や行
ら行
- ラクトトリペプチド ラクトフェリン リコピン リジン リノレン酸 緑茶 ルテイン ルンブルクスルベルス レシチン レスベラトロール レッドクローバー レッドパームオイル ローズ ローズヒップ ローヤルゼリー
わ行
-